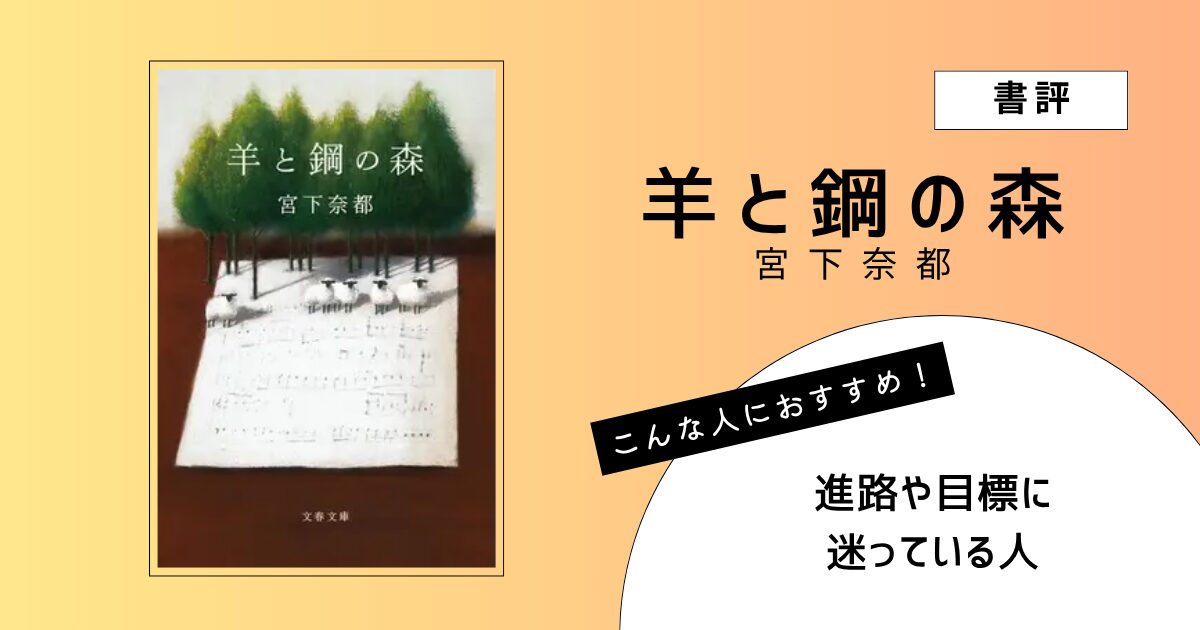みなさんは「ピアノ調律師」という仕事をご存じですか?
ピアノの調律や保守管理を専門に行う職業のことです。
楽器メーカーでピアノの設計や製作に携わる調律師の方もいるようですが、一般的には、学校や個人宅などでピアノの調律を行う仕事というイメージを持たれているかもしれません。
さて、今回ご紹介する本はこちら。
ピアノ調律師さんの物語。
『羊と鋼の森』(著者:宮下奈都)です。

こんな人におすすめ!
・進路や目標に迷っている人
・成長物語を丁寧な文章で味わいたい人
・音楽や職人仕事の世界を知りたい人
あらすじと補足
将来にこれといった目標もなく、なんとなく日々を過ごしていた男子高校生・外村。
そんな彼の前に現れたのは、学校にやってきた一人のピアノ調律師でした。
その出会いをきっかけに、外村は静かで奥深い「音の世界」へと惹かれていきます。
ピアノの内部には、柔らかい羊毛と硬い鋼が響きを生み出し、まるで森のように豊かな世界が広がっていました。
外村はその世界に足を踏み入れ、自分自身の耳で音を探り、少しずつ調律師としての道を歩み始めます。
ヤマモトは「調律師って絶対音感がないとできないのでは?」と思っていました。
でも主人公の外村にはそれがなく、代わりに「耳を澄ませる」ことで音をとらえ、自分なりの方法で答えを見つけていきます。
技術だけではなく、心の繊細さや感覚に支えられた職人の世界。
調律師という仕事の奥深さと、音に向き合うひたむきな青春が静かに描かれた作品です。
印象に残った場面
▶ 明るい音、澄んだ音。 華やかな音ってリクエストも多い
これは読んでいて驚かされました。
「明るい音」「澄んだ音」「華やかな音」
そんな抽象的なリクエストでも、調律師は応えてしまうのだそうです。
同じドレミの音でも、調律の仕方によって響きの雰囲気が変わるというのは、読んでいて本当に不思議でした。
実際に耳で確かめたわけではありませんが、文章を通して「音ってこんなに表情を変えるものなんだ」と知ることができ、音の世界の奥深さを感じました。
普段はただ「きれいな音」としか思わなかったピアノに、こんな多様な表情が隠れているとは…。
音楽に対する見方が少し変わるような場面でした。
▶ 《ラ》の音の基準は440ヘルツと決められている
普段何気なく耳にしている「ラ」に、ちゃんと数値で決められた基準があるなんて驚きです。
ちなみに、この440ヘルツは「国際標準ピッチ(A440)」と呼ばれるもので、1939年に国際的に採用されたそうです。
とはいえ歴史的には必ずしも一貫していたわけではなく、時代や地域によって「ラ」の音が少し高めだったり低めだったりしたこともあるとか。
そう考えると、今の「当たり前の音」も、実は長い歴史の中で選ばれた一つの基準にすぎないのだと感じて、なんだか不思議です。
440ヘルツといえば「悪魔の周波数」なんて呼ばれる都市伝説も耳にしますが、ピアノの調律に使われる440ヘルツは単純に「基準の音」という意味。
ちょっと怪しい響きとは無縁なんですね。
▶ 5月に雪
ヤマモトは雪国育ちなので、「5月に雪」という描写に思わず親近感がわきました。
5月といえば、もう春の空気に包まれている時期ですが、雪国では油断できません。
年によっては本当にどっさり降ることもあって、「ああ、わかる…!」と妙にリアルに感じられる場面でした。
「いったいどこの街が舞台なのだろう?」と気になって調べてみたところ、映画版は旭川で撮影されたそうです。
雪の季節感や空気感に説得力があるのも納得ですね。
作品の持つ静けさや透明感が、北国の風景とぴったり重なるように思えました。
▶ 一部表現が独特なところも
読んでいて、ときどき「これ、どういう意味だろう?」と立ち止まってしまうような表現がありました。
たとえば、
「美術館へ行くことが行事になる時点で何かをあきらめざるを得ない環境だったのだと今になればわかる」
という一文。
最初は「ん?」と思って読み返してしまったのですが、ヤマモトなりに解釈すると、
「本当は美術館なんて行きたくなかった。けれど行事だから行かざるを得ない」
=行きたい・行きたくないという本人の意思よりも、「環境に従わざるを得ない状況」を表しているのかな、と感じました。
ヤマモトは美術館が大好きなので、この文章を理解できなかったのかもしれません。
美術館に興味がない人が読めば、むしろ共感を覚える部分なのかもしれないな、とも思いました。
ちょっと独特な言い回しにしばらく考え込んでしまいましたが、こうした「一度引っかかる表現」もまた文学作品らしさのひとつかもしれません。
とはいえ全体的な文体は丁寧で読みやすく、難解すぎて投げ出してしまうようなことはありませんでした。
総評
▶ 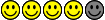
ピアノを弾いたことすらなかった主人公が、調律師という未知の世界へ一歩を踏み出す。
そこで待っていたのは、温かい励ましばかりではなく、お客さんや先輩からの厳しい言葉や試練の数々。
それでも挫けることなく、耳を澄まし、少しずつ前へ進んでいく姿に心を強く打たれます。
派手なドラマや劇的な成功ではなく、静かで地道な歩みの積み重ねだからこそ、読む人の胸に深く響くのだと思います。
主人公の姿からは、「強さ」とは大声で自己主張することではなく、静かに続けていく勇気なのだと教えられました。
自分も、こんなふうに一歩ずつでも前へ進んでいきたい…
そんな気持ちにさせてくれる作品です。
静かでありながら力強い、心に残る一冊。
おすすめです!
.png)