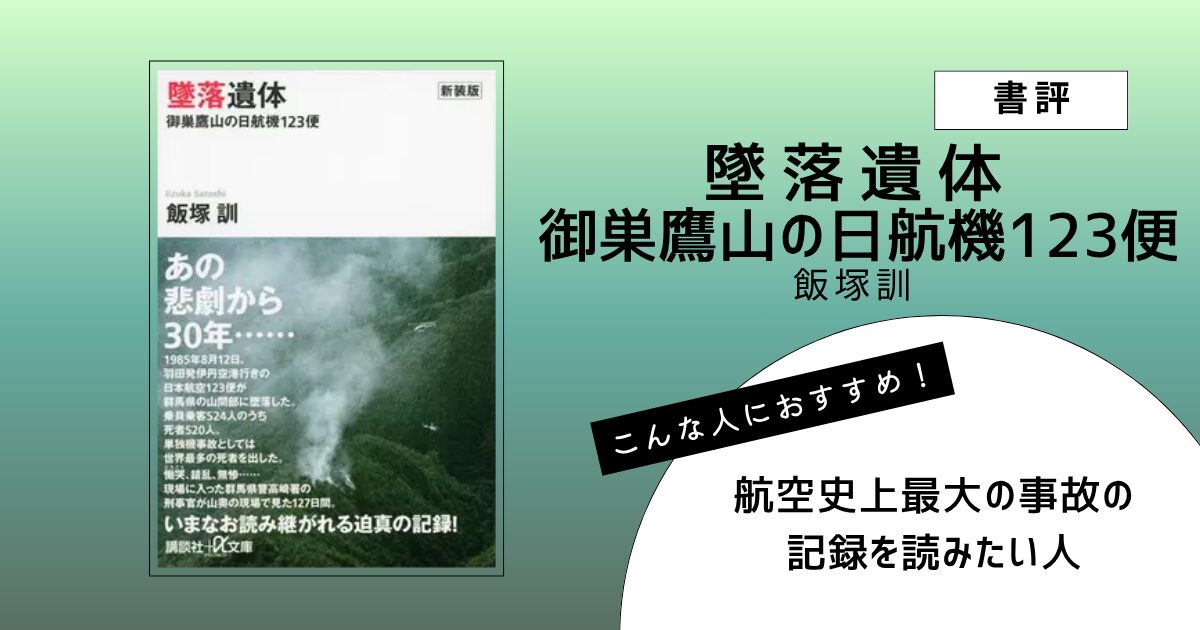みなさん、飛行機は好きですか?
ヤマモトは見るのも乗るのも好きですが、今回はそんな飛行機にまつわる痛ましい事故のノンフィクションをご紹介します。
『墜落遺体 御巣鷹山の日航機123便』(著者:飯塚訓) です。
1985年に起きた日本航空123便の墜落事故は、今なお「二度と繰り返してはならない悲劇」として語り継がれる未曾有の大惨事です。
本書は、その現場で遺体と向き合った一人の警察官による記録。
読むには勇気がいりますが、忘れてはならない出来事を静かに伝えてくれる一冊です。
出版された2015年当時は、事故からちょうど30年という節目にあたり、大きな反響を呼びました。

こんな人におすすめ!
・航空史上最大の事故の記録を読みたい人
・事故の舞台裏を知りたい人
・実際の事故の記録を真摯に受け止めたい人
あらすじと補足
1985年8月12日に発生した日航機123便の墜落事故。
単独機の事故としては世界最多の犠牲者を出し、今なお「二度と繰り返してはならない悲劇」として語り継がれています。
本書は、事故後から乗客全員の身元が確認されるまでの127日間を、克明に記録したノンフィクションです。
著者の飯塚訓氏は、当時、遺体の身元確認を統括する立場にあった警察官でした。
極限の現場で直面した現実や、遺族との向き合い方などが、余すところなく綴られています。
ページをめくるごとに「これはその場にいた人にしか書けない言葉だ」と痛感させられます。
事故の重さとともに、記録の意義を強く感じられる一冊です。
印象に残った場面
▶ 目次について
まず驚いたのは、本書の目次の細かさです。
なんと目次だけで7ページもありました。
その中には「完全遺体、離断遺体」「極度の悲しみが充満」「体に染みこむ臭い」といった、生々しい表現が並びます。
通常なら本文に出てくるような言葉が、見出しとして堂々と並んでいるのです。
ページを開く前から、事故現場がいかに過酷で壮絶だったかが伝わってきて、思わず息を呑みました。
目次だけでここまで緊張感を与える本は、なかなか無いと思います。
▶ 遺体の状態について
遺体の損傷がどれほど激しかったか、本書では驚くほど生々しく記録されています。
「頭の中に他の人の頭がめり込んでいる」
「頭部のない遺体の首のあたりにまとまっている皮を伸ばしてみると男性の顔だった」
といった記述は、読むだけで背筋が凍るものでした。
また、「土の中から臍の緒のついた嬰児が見つかり、事故の際に妊婦さんのお腹から飛び出た」と書かれており、胸が締めつけられる思いでした。
家族が変わり果てた姿と対面する場面や、墜落する機内で死を悟った男性が家族へ残したメッセージの場面は、ページをめくる手が止まらず、涙が出ました。
▶ 死後、身体はどうなる?
遺体に群がる蛆の様子まで細かく描写されていて、読んでいて思わずゾワッとしました💦
また、「遺体はメタンガスの発生で膨らみ、土気色から紫、そして黒へと変化していく」といった記述もあり、思わず九相図を連想しました。
(九相図とは… 屋外に打ち捨てられた死体が、朽ちていく様子を9段階で描いた仏教絵画のことです)
「自分も死んだら、やがて同じように変わっていくのだろうか」と想像してみると、現実味がなく不思議な気持ちになりました。
▶ 「 子ども 」
飯塚氏が「子供」ではなく「子ども」と書いている点が、とても印象に残りました。
「供」という字は「供養」や「供え物」といった言葉にも使われるため、どこか冷たい印象や死を連想させてしまいます。
とくにこの作品は、命を奪われた人々に寄り添いながら綴られているので、あえて「子ども」と書いていることに著者の思いを感じました。
123便の墜落事故では、未来を担うはずだった多くの子どもたちが犠牲になっています。
その事実に向き合う著者が、言葉の選び方ひとつにまで心を配っていることは、ただの文章表記の違い以上の重みを持つと感じました。
総評
▶ 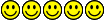
本書は飯塚氏の視点で書かれていますが、警察のことだけでなく、医師や看護師(当時は「看護婦」)
ボランティアの奮闘、そして悲しみに暮れる遺族の姿まで丁寧に描かれています。
目を背けたくなるような痛ましい描写も多いですが、それは紛れもなく実際に起きた出来事。
チームワーク、尊厳、情熱、命の尊さ。
ひとつひとつの場面に寄り添うような表現で記されており、胸に迫ります。
大変おすすめの一冊です。ぜひ多くの方に読んでもらいたいです。
.png)