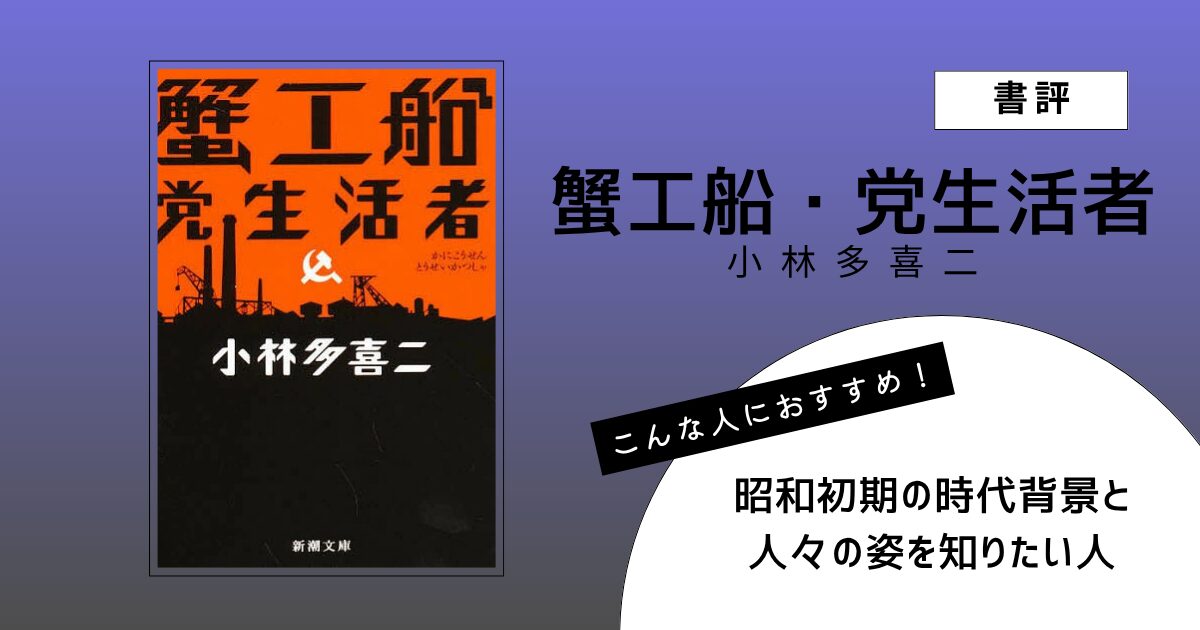今回ご紹介する本は、わたしたちが生まれるずっと前、昭和初期に書かれた作品。
『蟹工船・党生活者』(著者:小林多喜二) です。
本書は二本立てで、1929年に書かれた「蟹工船」と、1932年に書かれた「党生活者」が一冊に収められています。
どちらも「プロレタリア文学の傑作」と呼ばれる作品です。
プロレタリア文学とは、低賃金・劣悪な環境で働かされる労働者の姿を描いた文学のこと。
ウシジマくんやカイジなどに出てくるタコ部屋の話もプロレタリア文学。…たぶん。
こんな人におすすめ!
・昭和初期の時代背景と、人々の姿を知りたい人
・労働や格差、政治運動の歴史に関心がある人
・過酷な環境下で生きる人々の物語を知りたい人

あらすじと補足
「蟹工船」とは、カニを捕まえて手作業で缶詰に加工する工場を備えた漁船のこと。
毎日16時間にも及ぶ辛い労働、横暴な監督、不衛生な現場、飢えや体罰が横行し、死人が出る日々に立ち向かおうとする工員たちの「実話を元にした物語」です。
もう一作の「党生活者」は、共産党員として活動する人々の苦悩や葛藤を描いた作品で、軍需品を作る工場で臨時工として働きながら、工場内に党組織をつくろうとしている「私」が主人公。
虐げられているプロレタリアたちを救うため、ビラをまくなどの活動を行う社会主義者たちを描いています。
…と、内容は重厚で読みごたえ十分なんですが、
とにかく読みにくい!!😂
文体が昭和初期そのままなので、現代の小説に慣れていると
「ここ何て意味?」「一文長すぎ!」と何度もつまずきます。
正直、サクサクは読めません!
でもその「読みづらさ」自体が、当時の言葉遣いや空気感をそのまま閉じ込めている証拠なのかもしれません。
しんどいけど、「時代の息づかいを生で味わう」読書体験としては貴重な一冊です。
印象に残った場面(蟹工船)
▶ 見慣れない言葉が多い
「くさめ」や「いけホイド」など、馴染みのない言葉が出てきますが、注釈が無かったので Google 先生で調べながら読みました。
ヤマモトは新潮文庫版を読みましたが、注釈が無いためネット検索は必至です。
(他の出版社から出ている本には注釈があるかどうか不明😅)
ちなみに、「くさめ=くしゃみ」「いけホイド=行き倒れの乞食のよう」という意味らしいです!
また、「エレヴエター(エレベーター)」「オホツック海(オホーツク海)」など、現代とは違う表記も多く登場するので、おもしろいと思いました。
▶ バットが賞与?
脱走した労働者を捕まえた者に
「バット2つ、手拭1枚を賞与としてくれるべし」という張り紙があった、
という記述がありました。
ヤマモトは、てっきり野球のバットかと思い、
「え、なんでここで野球が?」と頭の中が「???」に。
ところが実際には、タバコの銘柄である「ゴールデンバット」のことだそうです😳
労働者の命が軽んじられた過酷な状況の中で、賞与として渡されるのがタバコや手拭い程度、という現実にも衝撃を受けました。
▶ 虫の描写がグロテスク
表現がグロいと聞いてはいましたが、実際に読んでみるとやはり衝撃的でした。
虱(しらみ)や南京虫が大量発生している様子、死体に蛆や蝿がわいている描写など、独特でなかなか気持ち悪い表現が続きます。
中でも「服に大量の虱がいる」といった記述にはゾッとしました。
「当時の蟹缶には、実際に虱が混じっていたのでは…」と想像してしまい、読んでいて背筋が寒くなりました🤢
印象に残った場面(党生活者)
▶ 蟹工船と比べると・・・
「蟹工船」のようなグロテスクな描写や強烈な見せ場は特にありません。
そのぶん淡々とした描写が続き、正直かなり読み進めるのが大変でした。
昭和初期特有の長い構文もあって、3行読んでは眠くなったり集中力が切れたり…。
ページ数は少ないはずなのに、読み切るまでに10日近くもかかってしまいました。
「蟹工船」も決して読みやすいとは言えませんが、強烈な場面がある分まだ印象に残りやすかったと思います。
それに比べると「党生活者」は見せ場が少ないぶん、さらに読みにくさが際立った作品でした。
▶ 感動的なシーン
見せ場が無い…と前述しましたが、ひとつ心に残った場面があります。
それは、母親が長く会えなかった息子にやっと会えたシーンです。
母親は再会の喜びに胸を熱くしながらも、同時に「自分と会ったことで息子を危険に晒してしまうのではないか」と不安に駆られ、早々に切り上げようとします。
せっかくの再会を素直に喜べないその姿に、母親の深い愛と苦しさが凝縮されています。
淡々とした全体の中で、このシーンだけはとても印象的でした。
総評
▶ 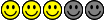
読みにくいところは多々ありましたが、実話をベースにしているため、ノンフィクションに近い迫力を感じました。
ただ、昭和初期の作品ということもあり、文章だけで理解するのは難しい部分が多く、読み進めるのに時間がかかりました。
そこでヤマモトは、漫画版の「蟹工船」と同時並行で読むことに。
活字だけではつかみにくかった労働環境や登場人物たちの姿が漫画で視覚化され、作品の世界を理解する助けになりました。
(「党生活者」の漫画もあればもっと理解が深まったと思いますが、党生活者の漫画は無いみたい…)
「蟹工船」は漫画版もいろいろ出ていますが、ヤマモトが読んだのはこちらの表紙の電子書籍です!
全体を通して、「文学としての価値は高いけれど、現代の読者にはやや敷居が高い一冊」という印象ですね😅
そして後日、函館旅行で函館市北洋資料館に行ってきました!
工船の模型や、実際に船で作られていた蟹の缶詰、北の海の生き物の剥製など、とても興味深くておもしろかったです!
川崎船(蟹工船のモデルとなった船)の乗り心地が体験もできるアトラクション?もあって、いかに過酷な環境だったのか窺い知ることができました。
北洋資料館は、五稜郭タワーの道路を挟んですぐ向かいの建物です。
入館料100円で駐車場2時間無料になるので、そのまま五稜郭も見に行くことができます。
蟹工船を読んでいない方も、資料館見学などに興味の無い方も、意外と楽しめると思うので、函館観光の際はぜひ!
.png)