ヤマモトは読書から少し離れていた時期があるのですが、その間に、過去に夢中で読んだ本の続編がいくつも発売されていました。
今回ご紹介する作品もそのひとつ。
『カササギ殺人事件(上)』(著者:アンソニー・ホロヴィッツ / 訳:山田蘭)です。
発売当時に読んで、ものすごくおもしろくて感動した一冊でした。
「この作者さんと訳者さんは間違いない!」と思い、その後『メインテーマは殺人』と『その裁きは死』も発売されてすぐ読み、
さらにアティカス・ピュントシリーズ続編の『ヨルガオ殺人事件(上・下)』まで購入。
ところが、そこでなぜか読書熱がプツリと途切れてしまいました。
そして数年後。
久しぶりに読書熱が戻ってきて、本屋さんに寄ってみたら、アティカス・ピュントシリーズ最新作『マーブル館殺人事件(上・下)』が並んでいるではありませんか。
「読みたい!」と思う反面、『カササギ』の内容はうろ覚えで、『ヨルガオ』に至っては未読。
せっかくならこの機会にシリーズを最初から読み直して、レビューも書いてみようと思い、まずは『カササギ殺人事件』を再読しました!

こんな人におすすめ!
・クラシカルな英国ミステリが好きな人
・作中作の世界に浸りたい人
・じっくり謎を追いたい人
あらすじと補足
物語は、編集の仕事をしている「わたし」(名前は下巻で明かされる)が、アティカス・ピュントシリーズ第9作『カササギ殺人事件』の原稿を読み始めるところから始まります。
作中作『カササギ殺人事件』は、地主の屋敷に仕える家政婦が階段から転落死するという、痛ましい事故(事件?)から幕を開けます。
村人たちそれぞれの視点で、故人とのやり取りや葬儀の様子、事故直後の行動や思考が断片的に描かれ、やがて第二の事件が発生。
そこからは、私立探偵アティカス・ピュントが登場し、点と点を繋ぎながら真相を追っていきます。
本作は、女性編集者である「わたし」が読む
「アラン・コンウェイという作家が書いた小説」という二重構造になっていて、作中作のミステリーと、それを取り巻く現実世界のドラマが巧みに交差します。
その原稿に触れたことで、彼女自身の周囲の環境や人間関係が変化していく。
その過程も見どころのひとつです。
印象に残った場面
▶ 久々の海外小説は名前との戦い
読み始めたものの、最初はなかなかページが進みませんでした。
活字を読むのって、やっぱり「慣れ」が必要だと思います。読書熱は戻ってきたものの、海外作品はやっぱり少し読みづらい。
登場人物が多く(登場人物紹介に23人!)
人名も「メアリ・エリザベス・ブラキストン」など長め。
地名も「サクスビー・オン・エイヴォン」といった具合で、馴染みがない。
加えて、日本にはない文化「村の緑地でクリケットをする」「土葬のための穴を掘る」などの描写や、
「お節介な人」を「すべてのパイに指を突っこむ人間」と表現する独特の言い回しもあり、最初は戸惑いました。
数年前に初めて読んだときは「めちゃくちゃおもしろい!」と感じたのですが、その頃は年間250冊ほど読んでいた時期。
海外作品にも慣れていたので、当時はスラスラ読めたんだと思います。
とはいえ、他の海外作品に比べれば登場人物はまだ少ない方。
しかも、通称や愛称も「ジョージー(ジョイ)・サンダーリング」のように登場人物紹介にしっかり書かれていて親切です。
ただ、これは訳ミスかもしれませんが、登場人物紹介では「ジェフ」となっていた人物が、本文では「ジェフリー」になっているところがあったり、
「ジョン」が「ジョニー」になっていたりと、微妙なズレがあり、少し混乱しました。
▶ 不幸の原因はいつも他人?
登場人物の中には、自身の不幸な境遇について「自分は悪くない」「何もしていないのに」「あいつのせいでこうなった」と、他人を責め続ける人が何人も出てきます。
読んでいて、「いやいや、自分の人生を何とかしようとしなかったのは自分でしょ!」とツッコミたくなる場面もしばしば。
もちろん気の毒な事情もあるんですが、何もしないまま不幸を嘆く人って実際いますよね。、
思わずイラッとしつつも、どこか現実味があるようにも感じました。
▶ ピュントの最後の一言にすべて持っていかれる
ストーリーが進むにつれ、複雑な人間模様や事件の断片が少しずつ繋がっていき、終盤でピュントが真相に迫ります。
そして上巻の最後、彼の一言で一気に空気が変わる。
「えっ!?どういうこと!?」と声が出そうになりました。
それまでの重いテーマや停滞感が、一瞬で「次が読みたくてたまらない」気持ちに変わる。
まさに、読者の心を転がす仕掛けの巧さに唸らされました。
総評
▶ 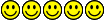
ポップな装丁とは裏腹に、物語は決して明るくありません。
人間の醜さや保身、本音と建前。
そうした「生々しい現実」を突きつけてくる一冊です。
再読にもかかわらず、あらためて感じたのはストーリーテリングの巧みさ。
序盤のゆるやかな語りから、ラストの衝撃的な一言までの流れが本当に見事でした。
人間の弱さと愚かさ、そしてその中に潜むわずかな希望。
それらが複雑に絡み合って、ページを閉じたあとも心に残ります。
上巻のラストで投げかけられた「あの一言」が、いったい何を意味するのか。
続きが気になる!😆
.png)
.jpg)
